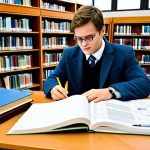建設材料試験技士の資格取得、本当に大変な挑戦ですよね。私もかつて受験生として、どの参考書を選べば最短で合格に辿り着けるのか、ずいぶん頭を悩ませた経験があります。書店に並ぶ膨大な数の参考書の中から「これだ!」と思える一冊を見つけ出すのは、まさに宝探しのようなもの。特に最近は、建設業界全体のDX化や環境配慮型素材の導入など、新しい技術やトレンドがどんどん生まれていて、試験範囲も以前とは比べ物にならないほど進化しているように感じます。古い情報ばかりの参考書では、今の試験の傾向に対応しきれないかもしれません。私が実際に何冊も購入し、時には失敗しながらも、最終的に「これは本当に役立った!」と心から思える参考書と出会えたので、その貴重な経験を皆さんと分かち合いたいと思います。下記記事で詳しく見ていきましょう。
建設材料試験技士の資格取得、本当に大変な挑戦ですよね。私もかつて受験生として、どの参考書を選べば最短で合格に辿り着けるのか、ずいぶん頭を悩ませた経験があります。書店に並ぶ膨大な数の参考書の中から「これだ!」と思える一冊を見つけ出すのは、まさに宝探しのようなもの。特に最近は、建設業界全体のDX化や環境配慮型素材の導入など、新しい技術やトレンドがどんどん生まれていて、試験範囲も以前とは比べ物にならないほど進化しているように感じます。古い情報ばかりの参考書では、今の試験の傾向に対応しきれないかもしれません。私が実際に何冊も購入し、時には失敗しながらも、最終的に「これは本当に役立った!」と心から思える参考書と出会えたので、その貴重な経験を皆さんと分かち合いたいと思います。下記記事で詳しく見ていきましょう。
試験範囲の変遷と最新トレンドへの対応術

私が受験生だった頃と比較しても、建設材料試験技士の試験範囲は驚くほど多様化し、深みを増していると肌で感じています。かつてはコンクリートや鋼材といった主要材料の基本特性が中心でしたが、今や環境配慮型材料、高性能繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材、さらにはBIM/CIMといったデジタル技術との連携に関する知識まで求められるようになりました。特に、近年注目されているリサイクル材料や、カーボンニュートラル社会に向けた低炭素コンクリートなどの分野は、試験に出る頻度が明らかに増えています。私も当初は「こんなところまで覚えるの!?」と途方に暮れたものですが、最新の業界動向にアンテナを張り、情報収集を怠らないことが合格への近道だと痛感しました。古い参考書だけに頼っていると、思わぬところで足をすくわれる可能性があるので、常に最新の情報をキャッチアップする意識が何よりも大切です。
1. 最新の出題傾向を掴む情報源
試験対策で一番大切なのは、やはり「傾向と対策」です。私がおすすめするのは、まず建設材料試験技士の公式サイトや関連団体の発表をこまめにチェックすること。過去の合格者の声を聞いたり、受験予備校の分析レポートに目を通したりするのも非常に有効です。私自身、最初は過去問ばかりに目を奪われていましたが、ある時、最新の国土交通省の技術基準改定が試験範囲に反映されることを知り、慌てて関連情報を集めた経験があります。特に、DX関連の技術や新しい試験方法については、業界誌や専門サイトのニュースを追うだけでも、試験のヒントが隠されていることがあります。「まさかここから出るなんて!」と驚くような問題も、実は日頃の情報収集でカバーできた、なんてこともあるんです。
2. 新技術・新素材へのアプローチ法
新しい技術や素材に関する知識は、座学だけではなかなか頭に入りにくいものです。私の場合、インターネットで関連動画を視聴したり、もし可能であれば建設現場の見学会に参加したりして、実際の使われ方や特性を目で見て学ぶようにしていました。例えば、高流動コンクリートや自己治癒コンクリートなど、名前は知っていても具体的なイメージが湧かない材料は、動画でその施工性や硬化過程を見るだけで理解度が格段に上がります。また、実際に使用されている新素材のパンフレットを取り寄せてみたり、メーカーのウェブサイトで技術資料を読み込んだりするのも非常に有効です。これらは試験対策だけでなく、将来のキャリアにも役立つ知識として、楽しみながら吸収する姿勢が大切だと感じました。
独学を成功させる!最適な参考書選びの秘訣
建設材料試験技士の資格取得を目指す上で、最も頭を悩ませるのが「どの参考書を選べばいいのか」ということではないでしょうか。私も書店でずらりと並んだ参考書を前に、どれが本当に自分に合っているのか分からず、何時間も立ち尽くした経験があります。中には「これ一冊で合格!」と謳いながら、内容が薄すぎたり、逆に詳しすぎて途中で挫折しそうになったりする本もありました。私の経験から言えるのは、最初から完璧な一冊を探すよりも、複数の参考書を組み合わせて弱点を補い合う「戦略的な選び方」が重要だということです。合格への遠回りを避けるためにも、以下のポイントを参考にしてみてください。
1. あなたに合った参考書を見つけるチェックリスト
参考書選びで失敗しないためには、まず自分の学習スタイルと現在の知識レベルを客観的に評価することが大切です。例えば、まったくの初心者であれば、基礎から丁寧に解説されている「入門書」を選ぶべきですし、ある程度の知識があるなら、問題演習に特化した「問題集」や「過去問解説書」が効果的です。私も最初は「とにかく分厚い本が良いに違いない!」と思い込み、内容を理解できずに途中で投げ出してしまったことがあります。大切なのは、読み進めるモチベーションを維持できるか、そして解説が自分にとって分かりやすいかどうかです。書店で実際に数ページ読んでみて、言葉遣いや図の多さ、レイアウトなどを確認することをおすすめします。
2. 複数使い分けのススメと選び方のポイント
一冊の参考書だけで試験範囲全てを網羅しようとするのは、実は非効率的です。私の場合、まず全体の流れを掴むための「基本書」を1冊、次に知識の定着と応用力を養うための「問題集」を2冊、そして直前対策として「過去問解説書」を1冊、というように役割分担をしていました。特に、問題集は解説が丁寧なものと、ひたすら問題数をこなせるものの2種類あると、飽きずに学習を続けられます。また、最新の試験傾向に対応しているか、法改正や新技術に関する情報がアップデートされているかも重要なポイントです。
| 参考書の種類 | 主な特徴と使い方 | 選び方のポイント |
|---|---|---|
| 基本書(テキスト) | 基礎知識の習得、全体像の把握。初めて学習する分野におすすめ。 | 解説の分かりやすさ、図やイラストの多さ、内容の網羅性。 |
| 問題集 | 知識の定着、応用力の育成。単元ごとの演習に最適。 | 問題数の豊富さ、丁寧な解説、間違いやすいポイントの指摘。 |
| 過去問解説集 | 試験形式の理解、時間配分の練習、出題傾向の把握。直前対策の切り札。 | 最新の過去問が収録されているか、詳細な解説、解答への導き方。 |
| サブテキスト・資料 | 苦手分野の克服、法規・基準など専門性の高い知識。 | 専門分野に特化しているか、信頼性のある情報源。 |
3. デジタル教材の活用法
最近では、紙の参考書だけでなく、オンライン講座やEラーニング、スマートフォンアプリといったデジタル教材も非常に充実しています。私自身、通勤時間やちょっとしたスキマ時間には、スマホアプリで一問一答を解いたり、オンラインで講義動画を視聴したりしていました。これが意外と馬鹿にならないんです。特に、動画教材は文字だけではイメージしにくい実験操作や材料の特性などを視覚的に理解できるため、記憶への定着が早かったと感じます。デジタル教材は、常に最新の情報に更新されやすいというメリットもありますし、何よりも場所を選ばずに学習できる手軽さが魅力です。ただし、情報過多になりがちなので、信頼できる情報源を見極める眼も養う必要がありますね。
過去問を徹底攻略!効率的な学習サイクルとは
建設材料試験技士の試験合格に向けて、過去問学習は避けて通れない道です。私自身、過去問を解き始めた頃は、まったく歯が立たなくて絶望しましたね。「こんなに難しいのか…」と心が折れそうになったのをよく覚えています。でも、そこであきらめずに試行錯誤を重ねた結果、ただ問題を解くだけではダメだということに気づきました。過去問を「効率的な学習ツール」として最大限に活用するためには、解きっぱなしにするのではなく、戦略的に取り組む必要があります。私の経験から導き出した、過去問徹底攻略のための学習サイクルをご紹介しましょう。
1. 「解く→見直す→理解する」の三段階学習
まず、過去問を解く際は、必ず時間を計って本番と同じ条件で行うことが重要です。そうすることで、自分の現在の実力と、時間配分の感覚を掴むことができます。次に、採点後が本当の勝負です。間違えた問題はもちろんのこと、たまたま正解した問題についても、解説を熟読し、なぜその答えになるのかを徹底的に理解するまで深掘りします。ここで大切なのは、「分からない」をそのままにしないこと。関連する参考書のページに戻ったり、インターネットで調べたりして、完全に理解するまで粘り強く取り組むべきです。この「解く→見直す→理解する」のサイクルを繰り返すことで、知識が点ではなく線として繋がり、応用力が身についていきます。私は間違えた問題には付箋を貼ったり、ノートに書き出したりして、後で何度も見返すようにしていました。
2. 苦手分野を見つけ、徹底的に潰す方法
過去問を何回か解いていくと、必ず「苦手な分野」が見えてきます。例えば、「コンクリートの配合設計は得意だけど、アスファルト混合物の試験方法になると途端に手が止まる」といった具合です。私の場合、特に力学系の問題が苦手で、毎回のように同じ種類の問題で失点していました。苦手分野を放置しておくと、本番でそこから出題されたときに致命傷になりかねません。そこで私は、苦手だと分かった分野を集中的に学習する期間を設けました。具体的には、その分野に関する基本書を読み直し、類題を解きまくり、それでも理解できない部分は、建設業界の先輩や友人に質問して教えてもらう、という泥臭い方法も取り入れました。苦手潰しは地味な作業ですが、得点アップに直結する最も効果的な戦略の一つです。
挫折を防ぐ!モチベーション維持とリフレッシュ法
資格試験の勉強は、長期戦になることがほとんどです。私も建設材料試験技士の学習を始めた当初は意気揚々としていましたが、途中であまりの範囲の広さと内容の難しさに、何度も「もう無理だ…」と心が折れそうになりました。特に仕事と両立しながらの学習は、時間的にも精神的にも大きな負担がかかります。しかし、そこで諦めてしまっては元も子もありません。私自身の経験から、挫折を防ぎ、合格まで走り抜けるためのモチベーション維持術と、効果的なリフレッシュ法をいくつかご紹介したいと思います。これは、勉強効率を高める上でも非常に重要な要素だと心底実感しています。
1. 小さな目標設定と達成感の積み重ね
「合格」という大きな目標だけを見据えていると、どうしても途中で息切れしてしまいます。そこで私が実践したのは、日々の学習に「小さな目標」を設定し、それをクリアするたびに達成感を味わうことでした。例えば、「今日はこの章の例題を全て解く」「この単元の問題を完璧にする」といった具体的な目標です。目標を達成したら、カレンダーにチェックを入れたり、自分へのご褒美として好きなデザートを食べたりするなど、ささやかながらもポジティブなフィードバックを与えるようにしました。この小さな成功体験の積み重ねが、次へのモチベーションに繋がり、気がつけば大きな目標へと着実に近づいていることを実感できるはずです。
2. 効率を上げる!適度な休憩とリフレッシュ法
「長時間ぶっ通しで勉強した方が効率が良い」と思われがちですが、私の経験上、それは誤りです。集中力には限界があり、無理に続けても効率は落ちる一方でした。私は25分勉強して5分休憩する「ポモドーロ・テクニック」を取り入れたり、1時間ごとに10分程度の休憩を挟んだりする習慣をつけました。休憩中には、温かい飲み物を飲んだり、ストレッチをしたり、窓から外の景色を眺めたりと、気分転換になることを意識的に行いました。また、週末には完全に勉強から離れて、趣味に没頭したり、友人と出かけたりする時間を設けることも大切です。心身をリフレッシュさせることで、次の週からまた新たな気持ちで勉強に取り組むことができ、結果的に学習効率が飛躍的に向上するのを実感しました。
実務経験がなくても大丈夫!初心者におすすめの勉強法
建設材料試験技士の資格取得を目指す方の中には、「自分は実務経験がないから不利なのでは?」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。私もまさにその一人で、初めて建設材料の試験に関するテキストを開いたときには、専門用語の多さに眩暈がするほどでした。「これは現場を知らないと理解できないのでは…」と、正直、何度も諦めかけました。しかし、結論から言うと、実務経験がなくても合格は十分に可能です。大切なのは、知識を体系的に、そして視覚的に理解しようと努めること。私が実際に試してみて効果があった、初心者におすすめの勉強法を詳しくご紹介します。
1. 基礎概念の徹底理解と用語の定着
実務経験がない場合、まずは「基礎の基礎」から固めることが何よりも重要です。専門用語は、単に丸暗記するのではなく、その意味するところ、それがなぜ必要なのかという背景まで理解しようと努めましょう。私の場合、各材料の試験方法については、なぜその試験を行うのか、その結果から何が分かるのか、という「目的」と「意義」を常に意識して学習しました。例えば、「スランプ試験」であれば、コンクリートの流動性を確認する試験である、そしてそれは施工性や品質管理に直結する、というように、知識を点ではなく線で繋げていくイメージです。分厚い参考書にいきなり挑むのではなく、まずは図や写真が多く、解説が丁寧な入門書から始めることを強くお勧めします。
2. 視覚情報を活用した理解促進
建設材料の試験は、実際の測定機器や手順をイメージしにくい部分が多いですよね。私もテキストの文字だけではなかなか頭に入らず、「実際にどういう動きをするんだろう?」と疑問に思うことが多々ありました。そこで非常に役立ったのが、YouTubeなどの動画サイトです。例えば、「引張試験」や「圧縮試験」といったキーワードで検索すると、実際の試験風景が多数アップロードされています。視覚的に手順や材料の挙動を捉えることで、テキストだけの学習では得られない深い理解が得られます。また、建設材料メーカーのウェブサイトでは、製品の特性や試験データが公開されていることもあり、これらを参考にすることで、より実践的な知識が身につきました。まるで自分が現場にいるかのようにイメージしながら学ぶことが、理解度を飛躍的に高める秘訣です。
3. 図書館やオンラインコミュニティの活用
実務経験がないからこそ、積極的に外部の力を借りることも重要です。私は地域の図書館で関連書籍を借りたり、時には専門書を置いてある大学図書館の利用を検討したりしました。また、オンラインの学習コミュニティやSNSで、同じ試験を目指す仲間を見つけるのも良い方法です。疑問点を質問したり、お互いの学習状況を共有したりすることで、モチベーションを維持しやすくなります。私自身、SNSで繋がった仲間と情報交換する中で、「この部分、テキストだけじゃわかりにくいけど、こう考えたらスッキリするよ」といった、目から鱗のアドバイスをもらえたことが何度もありました。一人で抱え込まず、積極的に交流することで、学習のヒントや突破口が見つかることもあります。
試験当日までの心構えと最終確認のポイント
いよいよ試験日が近づいてくると、誰もが緊張と不安でいっぱいになるものです。私も試験の1週間前からは、どうにも落ち着かず、夜もあまり眠れなかった記憶があります。それまでの努力が報われるかどうか、まさに運命の日ですからね。しかし、この直前期こそ、焦らず冷静に、そして計画的に過ごすことが何よりも重要です。付け焼き刃の知識で無理に詰め込もうとすると、かえって混乱を招きかねません。私が本番で最高のパフォーマンスを発揮するために意識したこと、そして直前に行った最終確認のポイントを、皆さんの不安を少しでも和らげるために共有したいと思います。
1. 直前対策は「新しいこと」より「基礎の徹底」
試験直前期に陥りがちなのが、「あれもこれもやらなきゃ」と焦って、今まで手をつけていなかった分野に手を広げてしまうことです。しかし、これは非常に危険です。私の経験上、直前期に新しい知識を詰め込もうとすると、かえってそれまでの学習内容が曖昧になり、混乱を招きやすくなります。この時期に最も効果的なのは、これまで学んできた「基礎知識」の総復習と定着です。特に、過去問で何度も間違えた問題や、苦手だと認識している分野に絞って、徹底的に見直すことが重要です。公式や定義、基本的な試験方法は、確実に押さえておくことで、本番での安定した得点に繋がります。私は直前に自分で作った苦手ノートを見返すことで、自信を持って試験に臨めました。
2. 試験前日の過ごし方と当日の持ち物チェック
試験前日は、心身を休ませることが最優先です。徹夜での追い込みは絶対に避けるべきです。頭をリフレッシュさせ、十分な睡眠を取ることで、脳が最高の状態で本番を迎えられます。私は前日には軽めの復習に留め、早めに床につき、ゆったりとした時間を過ごすように心がけました。そして、試験当日の朝は、慌てないように全ての準備を前日に済ませておくことが大切です。筆記用具、受験票、電卓(許可されている場合)、身分証明書はもちろんのこと、お昼ご飯や飲み物、チョコレートなどの軽食、そして寒さ対策や暑さ対策になるような衣類まで、抜かりなく準備しましょう。私が経験した中では、会場が予想以上に冷房が効いていて、集中できなかったという失敗談もあります。万全の準備が、試験当日の心のゆとりを生みます。
合格後を見据えて!資格が拓くキャリアパス
建設材料試験技士の資格は、取得がゴールではありません。むしろ、その資格があなたのキャリアに新たな扉を開き、未来を切り拓くための強力なツールとなります。私も合格した瞬間は、ただただ安堵の気持ちでいっぱいでしたが、時間が経つにつれて、この資格が自分の仕事にどれほどの価値をもたらしてくれるのか、その可能性にワクワクしました。資格取得を通じて得られるのは、専門知識だけではありません。自己成長への自信、業界内での信頼、そして新たな人脈といった、目に見えない財産も手に入れることができるのです。私の経験が、皆さんの合格後のキャリア形成の一助となれば幸いです。
1. 資格がもたらす専門家としての信頼と機会
建設材料試験技士の資格を持つということは、建設材料に関する深い専門知識と、それを実践する能力を国が認めている、という証です。これは、企業内での評価を高めるだけでなく、転職やキャリアアップを考える際にも非常に有利に働きます。私自身、資格取得後には、より専門性の高いプロジェクトへの参加を打診されたり、社内外の技術検討会で意見を求められたりする機会が増えました。以前は「一介の技術者」でしかなかった私が、「材料の専門家」として見られるようになったのは、この資格のおかげだと強く感じています。また、建設コンサルタントや材料メーカー、試験機関など、多様な業界での活躍の場が広がるのも、この資格の大きな魅力です。
2. 継続学習とキャリアの深化
建設材料の世界は、日々進化しています。新しい材料の開発、試験方法の改良、法改正など、常に最新の情報にアンテナを張っておく必要があります。資格を取得した後も、定期的に研修会に参加したり、専門誌を購読したりして、継続的に学習していく姿勢が重要です。私の場合、資格取得をきっかけに、さらに上位の資格を目指したり、特定の材料分野に特化して専門性を深めたりといった、具体的なキャリアプランが見えてきました。この資格は、ただ単に「持っているだけ」ではなく、それを生かして知識をアップデートし続けることで、あなたの市場価値をさらに高めていくことができる、そんな奥深いものです。
おわりに
建設材料試験技士の資格取得は、決して平坦な道のりではありません。私も受験生時代、何度も壁にぶつかり、心が折れそうになった経験があります。しかし、この資格を通じて得られる知識と、何よりも「やればできる」という自信は、あなたのキャリアを確実に次のステージへと引き上げてくれるはずです。この記事が、皆さんの合格への道のりを少しでも明るく照らし、そして何より、一人でも多くの方がこの素晴らしい資格に挑戦するきっかけとなれば、これほど嬉しいことはありません。諦めずに、一歩ずつ前に進んでいきましょう!
知っておくと役立つ情報
1. 試験範囲は常に変化しています。国土交通省の最新情報や業界ニュースにアンテナを張り、常にアップデートされた情報を取り入れましょう。
2. 参考書は一冊にこだわらず、基本書、問題集、過去問解説集など、用途に合わせて複数使い分けるのが効率的です。
3. 新しい技術や試験方法は、YouTubeなどの動画サイトで視覚的に学ぶと理解が深まります。
4. 勉強の合間には、必ず適度な休憩を取りましょう。リフレッシュすることで集中力が回復し、学習効率が向上します。
5. 資格はゴールではなく、キャリアのスタートラインです。取得後も継続的な学習で、自身の専門性を深めていきましょう。
重要ポイントまとめ
建設材料試験技士の資格取得には、最新の試験傾向への対応が不可欠です。環境配慮型材料やDX関連の知識など、試験範囲の変遷を把握し、公式サイトや専門誌で情報収集を怠らないことが重要です。独学を成功させるためには、ご自身の学習スタイルに合わせた参考書を複数組み合わせる「戦略的な選び方」が鍵となります。過去問は「解く・見直す・理解する」のサイクルを徹底し、苦手分野を克服することが合格への近道です。また、長期戦となる学習期間中は、小さな目標設定と適度な休憩でモチベーションを維持することが不可欠です。実務経験がない初心者の方も、基礎概念の徹底理解、視覚情報の活用、オンラインコミュニティの活用で十分に合格を目指せます。試験直前は新しい知識の詰め込みよりも基礎の徹底に集中し、前日は十分な休息を取りましょう。この資格は、取得後のキャリア形成において専門家としての信頼と新たな機会をもたらし、継続学習でさらなる市場価値を高めることが可能です。
よくある質問 (FAQ) 📖
質問: 最近の試験傾向としてDX化や環境配慮型素材の導入が進んでいるとのことですが、古い参考書ではなぜ対応しきれないのでしょうか?
回答: うーん、これね、本当にそうなんですよ。私が受験生だった頃も、書店で古い版と新しい版を見比べて「これ、どこが違うんだろう?」って悩んだんですけど、実際に手に取って中身を読んでみると、もう全く別物になっていると感じました。特に最近は、建設業界全体のDX化、つまりデジタル技術の導入が進んでいて、例えばBIM/CIMみたいな設計や施工管理の新しい手法が当たり前のように試験範囲に入ってきたり、環境配慮型素材、例えばリサイクル材を使ったコンクリートの強度試験とか、未利用資源の有効活用に関する知識が問われることも増えているんです。古い参考書だと、そもそもそういった技術や概念自体が載っていないか、載っていても情報が古くて今の基準に合わないことが多いんですよね。私が実際に経験したのは、過去問を解いていて「この用語、参考書にないぞ!?」って焦ったこと。結局、ネットで調べたり、最新版の専門書を買い直したりして、遠回りしちゃいました。だから、今の試験に対応するには、最新のトレンドをしっかり押さえているかどうかが本当に肝心なんです。
質問: 書店に並ぶ膨大な数の参考書の中から、「これだ!」と思える一冊を見つけ出すコツや、私が実践した選び方があれば教えてください。
回答: これ、まさに「宝探し」ですよね!私も何冊も立ち読みして、時には買って失敗もしながら、ようやく自分に合った一冊を見つけ出した経験があります。私が最終的に「これだ!」と感じた選び方は、まず「目次」と「図解の多さ」と「例題の質」でした。膨大な数の中から絞り込むには、まず目次を見て、自分の苦手な分野や、テキストで触れられている「DX化」や「環境配慮型素材」のような最新トピックが網羅されているかを確認します。次に、パッと開いたページの図やグラフが、直感的に理解しやすいか。文字ばかりで説明されていても、建設材料試験のような分野は具体的なイメージが湧かないと頭に入ってきにくいんですよ。そして一番重要だと感じたのが、各章の終わりに載っている例題の質と解説の丁寧さ。ただ答えが載っているだけでなく、「なぜそうなるのか」がきちんと説明されているか、違う解法も示されているか、みたいな点がすごく役立ちました。最終的には、何冊か候補を絞って、実際に少し声に出して読んでみて、「これなら毎日続けられそう」と感じる、相性みたいな直感を信じるのも大事だと思いますよ。
質問: 建設材料試験技士の資格取得、本当に大変な挑戦とのことですが、著者が試験勉強で「挫折しそうになった」具体的なエピソードがあれば教えてください。
回答: ええ、本当に大変でしたね。正直、何度も「もう無理だ…」って挫折しそうになりましたよ。一番記憶に残っているのは、仕事が終わってクタクタの状態で参考書を開いても、専門用語の羅列と複雑な計算式ばかりが目に飛び込んできて、全く頭に入ってこなかった時のことです。ある夜、徹夜で勉強しようと意気込んでコーヒーを何杯も飲んで始めたのに、ふと気づくと朝方、参考書を枕に寝落ちてしまっていて。目が覚めた時の絶望感と、全然進んでない現実に、本当に情けなくなって、本を放り出したくなりましたね。「こんなんじゃ一生受からないんじゃないか…」って本気で思いました。でも、それでも何とか机に向かい続けられたのは、「今回落ちたらまたあの勉強を最初からやり直すのか…」という、再受験の面倒くささが背中を押してくれたのと(笑)、何より「この資格を取って、自分の仕事の幅を広げたい!」っていう強い気持ちがあったからだと思います。あの時の苦しみがあったからこそ、合格した時の喜びはひとしおでしたし、今でもあの時の経験が自分の財産になっていると感じています。
📚 参考資料
ウィキペディア百科事典
구글 검색 결과
구글 검색 결과
구글 검색 결과
구글 검색 결과
시험 준비를 위한 추천 도서 – Yahoo Japan 検索結果